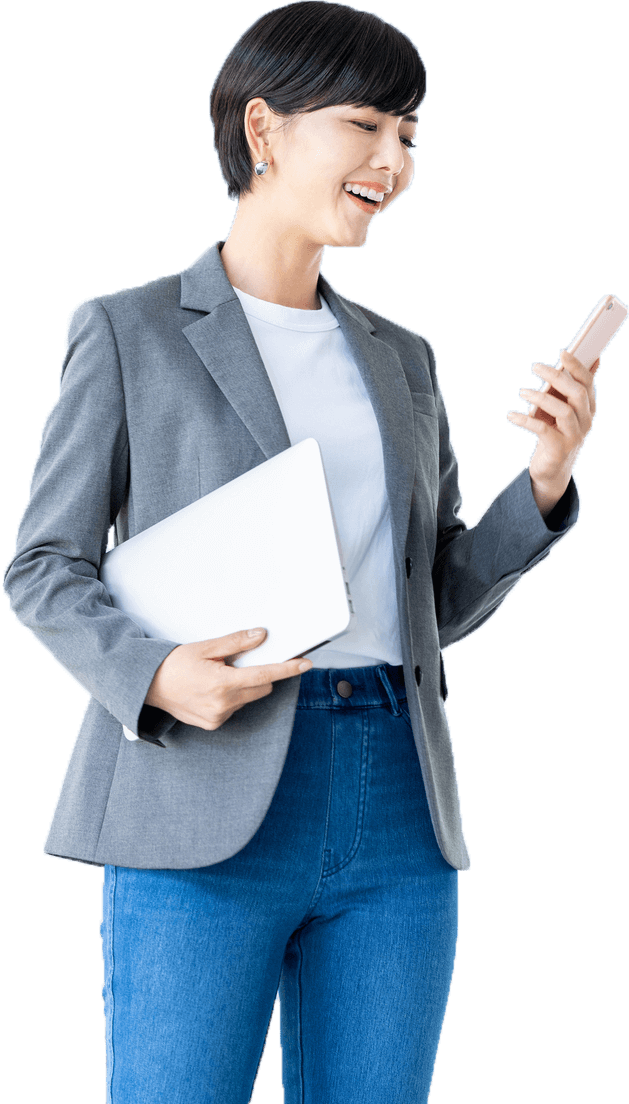コンサートスタッフとは?役割と魅力をざっくり紹介
コンサートスタッフとは、アーティストのライブや音楽フェス、アイドルイベントなどの現場で、イベントの成功を裏から支える存在です。観客の安全確保、ステージの設営・撤去、機材の搬入、アーティストのサポートなど、さまざまなポジションがあり、「コンサートをつくる」一員として不可欠な役割を担います。
華やかなステージの裏側には、多くのスタッフが連携しながら動く現場が広がっています。まさに、裏方こそがライブを成り立たせているのです。
ここでは、どんな現場で活躍できるのか、そしてスタッフとして働くうえでの魅力について詳しく紹介します。
ライブ・フェス・アイドルイベント…どんな現場で活躍する?
コンサートスタッフが活躍するのは、音楽ライブだけではありません。野外フェス、アリーナ公演、ホールでの演奏会、地下アイドルの対バンイベント、さらに舞台イベントや企業主催のスペシャルライブなど、実に多彩な現場があります。
夏の大型フェスでは、数万人規模の会場を一から設営・撤去したり、炎天下での誘導が必要だったりとハードな面もあります。一方で、ホールライブや企業系イベントでは、空調完備の屋内で比較的落ち着いて業務ができる場合も。
現場によって仕事内容や求められる対応が異なるため、自分に合ったスタイルの仕事を選びやすいのもコンサートスタッフの魅力のひとつです。
裏方だけじゃない!ステージ成功を支えるやりがいとは?
コンサートスタッフの魅力は、まさに“ステージの一部になれる”こと。自分たちが設営したステージで、観客が盛り上がり、アーティストが最高のパフォーマンスを見せている――その瞬間に立ち会えるのは、何ものにも代えがたい経験です。
また、観客からの「ありがとう」「助かりました」という言葉や、スムーズな運営ができたときの達成感は、アルバイトであっても十分に感じられるやりがいです。
単なる肉体労働ではなく、「安全を守る」「イベントを成功させる」というチームワークが重視される現場だからこそ、責任感と誇りを持って働ける仕事でもあります。
仕事内容を徹底解剖!どんな業務があるの?
コンサートスタッフと一口に言っても、業務内容は多岐にわたります。ステージの設営・撤去から、お客さまの誘導、アーティストのケア、さらには専門的な機材の搬入や操作の補助まで、それぞれの役割がライブを支えています。
ここでは、実際に現場で行われる業務を種類別に紹介していきます。自分に向いているポジションや、挑戦してみたい仕事をイメージする参考にしてください。
設営・撤去スタッフ:会場をゼロから作る縁の下の力持ち
設営・撤去スタッフは、まさに“現場の土台”を作る存在。ライブ会場のステージや照明タワー、観客席の設置、バリケードの設営、看板の取り付けなどを担当します。
ライブ当日の朝早くから集合し、会場を「何もない状態」から「本番を迎えられる状態」にまで作り上げる重要な役割です。終演後にはそれをすべて解体し、撤収作業も行います。
重い機材を運ぶことも多く、体力勝負な一面もありますが、「自分が作ったステージでライブが行われる」という達成感はひとしお。未経験でもできる仕事ですが、安全確認と指示への迅速な対応が求められます。
会場誘導・案内スタッフ:お客さんと最前線で関わるポジション
このポジションは、観客と直接関わる“顔”的な存在。チケットのもぎり、座席案内、入退場の誘導、整列の管理、トイレや物販場所の案内など、会場内外のあらゆる場面で活躍します。
イベントによっては外国人観客への対応や、トラブル対応などが求められることもあり、臨機応変な判断やコミュニケーション能力が役立ちます。
笑顔や丁寧な応対が印象に残る仕事であり、お客さんの「楽しかった!」という気持ちを直接感じ取れるのも大きな魅力です。
楽屋・アーティスト対応:関係者エリアでの気配り力が鍵
アーティストや関係者専用エリアでのサポートを行うスタッフは、裏方の中でも繊細な気配りが求められるポジションです。楽屋の案内、食事やドリンクの準備、移動の誘導、関係者以外の立ち入り管理などを担当します。
アーティストに直接接する機会もありますが、ファン感情は一切禁止。あくまで「運営スタッフとしての対応」が基本です。
機密性の高いエリアでの勤務になるため、守秘義務やマナーへの理解がある人に向いています。
機材搬入・照明・音響補助:専門的な現場もアリ!
音響機材、照明機材、大型スクリーンなどのテクニカルな機器を運搬・設置・接続するスタッフです。専門職の技術スタッフの指示を受けて、サポート役として動くことが多いです。
ある程度機材の名前や取り扱いを覚える必要はありますが、未経験でも慣れてくれば「このケーブルどこに通すか分かる」など自信がついてきます。
将来的に舞台技術の仕事に進みたい人にとっては、現場で直接学べる貴重なチャンスとも言えるでしょう。
1日の流れをイメージしよう!タイムスケジュール例
コンサートスタッフの現場は、早朝集合から深夜解散まで、長時間にわたることも少なくありません。全体の流れをあらかじめイメージしておくことで、体力配分や準備物、心構えもグッとしやすくなります。
ここでは、典型的な「ライブ当日1日の流れ」を、ステージ設営〜本番〜撤収までの流れに沿って紹介します。もちろん現場や担当ポジションによって差はありますが、おおまかなイメージを掴むのに役立ちます。
朝集合〜設営スタート
コンサートスタッフの1日は、早朝から始まることが多いです。集合時間はイベントによって異なりますが、6〜8時に現場入りすることも珍しくありません。
まずは点呼や朝礼で当日の流れと注意事項を確認。全員にスタッフパスが配られ、持ち場や役割分担が発表されます。
その後、ステージや音響、照明機材の搬入・設営作業がスタート。重い機材を扱うこともあり、安全確認をしながら進めるのが基本です。力仕事が多く、午前中の段階でかなり体力を使う場合もあります。
開場中の業務内容と注意点
設営が終わると、いよいよ開場。開場前にはお客さんが列を作り始めるので、誘導スタッフは列整理や注意事項のアナウンスなどを担当します。
開場後は、チケットのもぎり、座席への案内、フロア内の巡回、トラブル対応など、各ポジションで持ち場につきます。
この時間帯は最も慌ただしく、観客対応も多くなるので緊張感が高まります。声がけのトーンや言葉遣い、安全への配慮など、細かな対応が求められます。観客の満足度を左右する重要な時間帯です。
終演後の撤収作業と解散までの流れ
ライブが終わったら、観客を安全かつスムーズに退場させるのが最優先。規模が大きいイベントほど、トラブル防止のための慎重な対応が必要になります。
お客さんが完全に退場したら、今度はスタッフ総出で撤収作業に入ります。機材を片付け、バリケードや照明・音響設備を解体して、トラックに積み込むところまでが仕事です。
終演が夜9時〜10時ごろでも、撤収まで含めると解散は深夜になることもあります。とはいえ、終わったあとの「やりきった感」は格別。全員で作り上げた達成感を共有できる瞬間でもあります。
体力勝負?休憩・食事事情をリアルに紹介
「コンサートスタッフってきついって聞くけど、ちゃんと休憩取れるの?」と心配になる人も多いはず。実際、立ち仕事や力仕事が中心となるため、体力面の不安はつきものです。
でも安心してほしいのは、現場ではスタッフの健康や安全を考慮した休憩や食事の体制がしっかりと整えられていることがほとんど。ここでは、実際の休憩時間の取り方やごはん事情、現場ならではの“気をつけたい装備”まで紹介していきます!
休憩時間ってちゃんとある?
基本的にどの現場でも、定期的な休憩時間はしっかり確保されます。たとえば設営中なら「2〜3時間作業→15〜30分休憩」というペースが多く、開場中も持ち場を交代しながら順番に休憩を取るスタイルが一般的。
特に屋外イベントでは熱中症対策として頻繁な水分補給や小休憩が促されます。ただし、作業の進行状況や会場の混雑状況によってタイミングが多少前後することはあるので、臨機応変な対応が求められます。
お弁当・ドリンクは支給される?
イベント規模や運営会社によって異なりますが、お弁当やペットボトル飲料の支給がある現場は多いです。
昼食+夕食が提供されるケースや、軽食とドリンク数本を配られるケースなど、待遇の幅は広め。
ただし、「持参推奨」とされる現場もあるため、事前の案内をよく確認しておくのが大事です。中には「飲み物だけは自分で多めに持ってきて!」という場合もあるので、特に夏場や長丁場の現場では要注意!
夏フェス・冬ライブで気をつけたい服装&持ち物
現場にふさわしい服装と装備は超重要!特に**屋外イベントでは季節に応じた準備が生死を分ける(大げさじゃなく!)**ってレベルです。
夏フェス対策:
速乾性のTシャツ・通気性のいい長袖
タオル&帽子(熱中症防止)
飲み物多め(塩分入り推奨)
替えのTシャツ・制汗シート
冬イベント対策:
暖かいインナー+防寒着(ダウンや中綿入りジャンパー)
手袋&カイロ(休憩中に冷える)
靴下2枚重ね or 防寒ブーツ
未経験でも働ける?応募方法と始め方
「コンサートスタッフの仕事に興味があるけれど、経験がない自分でも大丈夫だろうか?」と不安に思う方は多いかもしれません。ですが実際には、未経験からスタートするスタッフが非常に多く、特別なスキルや資格がなくても始められる仕事が多数あります。
この章では、未経験から始められる理由や求められる人物像、具体的な応募方法、登録型派遣の仕組みなどについて詳しく解説します。初めての方でも安心して一歩を踏み出せるように、実際の流れや注意点も丁寧に紹介しています。
必要な資格やスキルはある?
基本的に、コンサートスタッフの仕事に就くために特別な資格や経験は必要ありません。未経験者歓迎の現場も多く、業務内容も当日現場で丁寧に説明されるため、初めての方でも安心してスタートできます。
ただし、円滑に仕事をこなす上で次のような素質やスキルを持っているとよりスムーズです。
体力に自信があること(設営や撤去などでは特に重要)
指示をしっかりと聞き、正確に行動できる
チームで動く仕事に抵抗がなく、協調性がある
接客や人とのコミュニケーションに一定の慣れがある(案内業務など)
なお、フォークリフトの操作や高所作業といった一部の業務では資格が必要となる場合もありますが、それはあくまでキャリアアップを目指す場合や、専門性の高いポジションに限られます。
学生・副業でもできる?年齢制限は?
コンサートスタッフの仕事は、学生や副業として働く社会人にも広く門戸が開かれています。特にライブやフェスが集中する土日祝や大型連休には、短期・単発の仕事が多く募集されているため、スケジュールに合わせて柔軟に働くことが可能です。
大学生の場合は、授業がない日や長期休暇中を活用して働く人が多く、現場には20代のスタッフが多く見られます。副業希望の社会人でも、夜間の公演や週末開催のイベントに対応しやすいため、収入を補いたいという目的でも選ばれる傾向があります。
なお、ほとんどの現場では高校生の勤務が不可となっているため、原則として18歳以上が対象となります。上限年齢の制限は特に設けられていませんが、体力的に負担がかかる作業も多いため、健康面への配慮は必要です。
どこで求人を探せばいい?おすすめサイト&派遣会社
コンサートスタッフの求人は、複数の手段で見つけることができます。以下の2つが主な方法です。
・求人情報サイト
タウンワーク
バイトル
マイナビバイト
フロムエー
これらの求人サイトでは「コンサートスタッフ」「イベントスタッフ」「ライブスタッフ」などのキーワードで検索することで、案件が多数見つかります。短期・単発・未経験OKなどの条件で絞り込みも可能です。
・イベント系派遣会社
以下のような派遣会社では、イベント系専門のスタッフを募集しており、事前に登録しておくことで、定期的に仕事の紹介を受けることができます。
株式会社フリージョン
株式会社ケイアンドケイプロデュース
株式会社シミズオクト
株式会社ユニティー
登録後はアプリやLINEを通じて仕事の案内が届くシステムを採用している会社もあり、勤務可能な日を選んで応募するだけで仕事が決まるという手軽さが魅力です。
登録制の仕組みや当日の流れを解説
イベントスタッフの仕事の多くは、登録制の派遣会社を通して募集されています。登録制とは、まず派遣会社に登録し、その後、自分の都合に合わせて仕事を選んで勤務するスタイルのことを指します。
具体的な流れは以下の通りです。
派遣会社の登録会に参加する、またはWEBで基本情報を入力して登録を完了させる
スケジュール入力や希望条件(勤務地・職種など)を提出する
勤務可能な日に合わせて案件が紹介され、希望の仕事にエントリー
勤務日当日、指定の時間・場所に集合してスタッフパスを受け取り、業務開始
現場では初めての方でもわかりやすいように説明があり、リーダーや先輩スタッフがフォローについてくれるため、安心して働くことができます。ただし、早朝集合や深夜終了など、拘束時間が長くなる可能性もあるため、事前にスケジュールと体調管理をしっかり行うことが大切です。
リアルな声!実際に働いた人の体験談
実際にコンサートスタッフとして働いたことのある人の声は、求人情報やマニュアルでは分からない“現場のリアル”を知るための大きな手がかりになります。
このセクションでは、良かった点・大変だった点・初心者がつまずきやすいポイントなど、実際の現場経験者の体験談をもとにまとめています。これから始めようと思っている方が、具体的なイメージを持てるような内容になっています。
楽しかったこと・感動した瞬間ベスト3
スタッフとして働くなかで、「やって良かった」「また入りたい」と感じる瞬間は多々あります。以下は、現場経験者が実際に挙げた“感動した出来事”です。
1. ステージが完成した瞬間の達成感
朝から作業して完成したステージを前に、観客が入って盛り上がる光景を見たとき、自分の仕事が確実に形になったと感じられる。
2. お客様からの「ありがとう」
会場案内や誘導業務中に「助かりました」「楽しかったです」と直接声をかけられたときは、大変さが一気に報われる瞬間です。
3. バックステージでの緊張感と一体感
アーティストがステージに立つ直前の張り詰めた空気感を間近で感じられるのは、スタッフならではの特権。関係者全員が一つの目標に向かって集中する時間に、自分もその一員として関わっていることを実感できます。
正直キツかった場面・大変だったこと
もちろん、良いことばかりではありません。現場によっては厳しいと感じる瞬間もあります。
長時間立ちっぱなし
特に誘導や警備系のポジションでは、座る時間が少なく、終演までずっと立ち仕事ということもあります。
気温・天候の影響
屋外フェスでは、夏場の猛暑や冬の寒さが大きな負担になります。天候に左右される現場では、装備や体調管理の重要性を痛感するという声も多いです。
急な変更や指示に対応する難しさ
現場ではスケジュールや指示が突然変更されることもあります。柔軟に動けるかどうかで、自分のストレス度合いが変わってくると感じる人も多いようです。
芸能人って本当に見れる?
「アーティストに会えるかも」という期待で応募する方も多いですが、実際のところは“ケースバイケース”です。
たとえば楽屋対応やバックステージ誘導など、一部のポジションではアーティストを直接見る機会があることもあります。しかし、原則として「業務上必要な接触以外は禁止」とされており、握手や写真撮影、サインを求めるなどの行為は固く禁じられています。
見かけたとしても、あくまで「業務として関わる」スタンスを保てる人でないと、現場に立つことは難しいと考えた方が良いでしょう。
初心者がやりがちな失敗と対策
初めての現場でよく見られるミスや失敗と、それを防ぐための対策は以下の通りです。
1. 集合時間に遅れる
集合時間に1分でも遅れると、その日の現場に入れないこともあります。前日夜には持ち物と経路を必ず確認し、時間に余裕をもって出発しましょう。
2. 指示が聞き取れない・理解できない
現場ではインカムや無線で指示が飛ぶことがあります。事前に業務内容をしっかり把握し、分からないことは素直に確認することが大切です。
3. 身だしなみ・服装がNGになる
派手な髪色、露出の多い服装、運動に不向きな靴などは現場NGとなることがあります。事前に服装規定を確認しておきましょう。
気になる給料・待遇をチェック
コンサートスタッフの仕事は、単発や短期でも比較的高い日給が見込めることから、学生や副業希望の方からも人気があります。ただし、仕事内容や拘束時間によって実際の金額は大きく変動します。
このセクションでは、時給・日給の目安から、交通費や手当の有無、さらに“意外と気になる”報酬の仕組みまで詳しく解説します。働く前にしっかり確認しておくことで、トラブルの防止や納得感のある就業につながります。
日給・時給の相場は?
コンサートスタッフの給与体系は、主に「日給制」と「時給制」に分かれます。多くの現場では日給制が一般的で、1日あたりの拘束時間によって報酬が決まります。
設営・撤収を含むフルシフト(10〜12時間程度):日給10,000〜14,000円前後
開場〜終演の短時間勤務(4〜6時間程度):日給5,000〜8,000円前後
一方、時給制の現場では、1,100〜1,400円程度が相場ですが、深夜や早朝など割増対象の時間帯がある場合は、さらに高くなることもあります。
給与は「月払い」「週払い」「日払い」など派遣会社や契約形態によって異なるため、応募前に確認しておくと安心です。
交通費・食費・深夜手当の有無
待遇面で気になるポイントとして、以下の3つを事前に確認しておくことが重要です。
交通費
全額支給、一定額まで支給、自費負担のいずれか。首都圏では「上限1,000円まで」などの条件付き支給が多く見られます。
食費(弁当支給)
イベントによっては昼・夜に弁当が支給されることもありますが、「なし」の現場もあるため、持参が必要なケースもあります。
深夜手当
22時以降の作業がある場合、労働基準法に基づき深夜手当(時給25%増)が支払われるのが原則です。ただし、契約内容により異なる場合もあるため、就業前に必ず確認しましょう。
拘束時間や「早く終わっても同じ給料」って本当?
コンサートスタッフの仕事では、「予定より早く業務が終わったが、当初の報酬はそのまま支払われた」というケースが珍しくありません。これは、あらかじめ「この仕事は◯時間でいくら」と定められた日給制の特徴によるものです。
一方で、「業務が長引いても延長料金が出ない」という現場も存在するため、拘束時間に対する報酬の仕組みは事前確認が必須です。契約内容や労働条件通知書に目を通しておくことをおすすめします。
また、「待機時間」や「準備時間」が拘束時間に含まれるかどうかも、実際の現場では重要なポイントになります。余裕を持ったスケジュール管理が必要です。
将来につながる?コンサートスタッフのキャリアパス
コンサートスタッフの仕事は、単発・短期のアルバイトとして始める方が多い一方で、「イベント業界でキャリアを積みたい」「将来的には制作や演出に関わりたい」という方にとって、重要な“第一歩”となる現場でもあります。
ここでは、アルバイトから正社員・専門職への道、イベントディレクターなど上位職へのステップアップ、そして他業界でも活かせるスキルまで、将来につながる可能性を幅広く解説します。
バイトから正社員へステップアップは可能?
可能です。実際、多くのイベント制作会社では、アルバイトとして現場経験を積んだ人材を正社員として登用するケースがあります。
継続的にシフトに入り、現場での信頼を積み重ねることで、「アシスタントディレクター」や「進行管理補佐」などのポジションに声がかかることもあります。特にイベントごとの人材リピート率が高い派遣会社や制作会社では、社内昇格のルートが明確に用意されている場合もあります。
また、他社のイベント現場でスカウトされるといったケースもあり、「現場を真面目にこなす姿勢」は大きなアピール材料になります。
イベントディレクターや制作進行を目指すには?
イベントディレクターや制作進行を目指すには、まず現場スタッフとしての基礎経験が不可欠です。設営や誘導だけでなく、タイムテーブルの管理、各部門との連携、リスク対応などの“運営の視点”を学んでいく必要があります。
アルバイト経験を通して以下のスキルを高めることで、ステップアップが可能になります。
現場全体の流れを俯瞰する力
トラブル時の対応力
チームをまとめるリーダーシップ
正確な報告・連絡・相談のスキル
ディレクターや制作進行は、現場で指示を出す立場になるため、単なる作業者から「管理側」への意識転換が求められます。長期的にイベント業界で働きたい人にとっては、目指す価値のあるキャリアです。
他業種でも活きるスキルとは?
コンサートスタッフとして培われるスキルは、イベント業界にとどまらず、他業種でも通用するものが多くあります。
例えば、
臨機応変な対応力(接客・営業職)
マルチタスクの処理能力(事務・運営管理)
体力と集中力(物流・製造現場など)
チームワークや指示理解力(医療・介護・教育現場)
また、人前での対応や接遇の場面も多く、自然とコミュニケーションスキルが身につく点も大きな特徴です。
イベントスタッフの経験は、職務経歴書や面接でもアピールできる立派な実績になります。特に「困難な場面をどう乗り越えたか」といったエピソードは、どんな職種でも評価されやすいポイントです。
よくある質問(FAQ)
ここでは、コンサートスタッフに関してよく寄せられる疑問や不安を、Q&A形式でまとめました。未経験者の方やこれから応募を検討している方が、安心して一歩を踏み出せるように、実際の現場経験や業界事情に基づいて回答しています。
コンサートスタッフの仕事内容は?
仕事内容は多岐にわたりますが、大きく分けて「設営・撤去作業」「会場誘導・案内」「バックステージ対応」「機材搬入・技術補助」などがあります。公演前は会場の準備やお客様の案内、終演後は機材や設備の撤収作業などが主な業務となります。
コンサートスタッフに向いている人は?
体力に自信がある方、チームで協力して作業するのが得意な方、指示を正確に聞いて動ける方には特に向いています。また、時間厳守や基本的な礼儀を守れる方、接客に苦手意識がない方も歓迎される傾向があります。
コンサートスタッフの年収はいくらですか?
基本的にはアルバイト・単発の仕事が多いため、年収は勤務頻度によって大きく異なります。週3〜4日ほど勤務した場合、月収で10万円〜15万円前後、年収にすると120万円〜180万円程度になることが多いです。正社員や契約社員として制作会社に所属した場合は、年収300万〜450万円程度が目安です。
コンサートスタッフになるためにはどうすればいいですか?
求人サイトやイベント専門の派遣会社を通じて応募するのが一般的です。多くの派遣会社では登録制を採用しており、WEB登録または登録説明会に参加してから、勤務可能日を申請し、仕事を紹介される流れとなります。特別な資格は不要で、未経験でも問題なく始められます。
男女比や年齢層はどれくらい?
現場によって異なりますが、男女比はおおむね半々からやや男性が多め。設営や撤去など力仕事の多いポジションでは男性が多く、案内や受付など接客を伴う業務では女性が多い傾向があります。年齢層は20〜30代が中心ですが、40代以上のベテランスタッフが活躍している現場もあります。
短期・単発でも応募できる?
はい、むしろ短期・単発の募集が多いのがこの仕事の特徴です。イベントごとにスタッフを募集するため、1日だけ・週末だけの勤務も可能です。学業や本業と両立しやすいことから、学生や副業希望の方にも人気があります。
本記事の内容は一般的な参考情報として提供されています。掲載されている情報の利用は、ご自身の判断と責任において行ってください。
当社は、掲載情報の正確性や最新性について保証するものではなく、これらの情報に基づく行動やその結果について一切の責任を負いません。